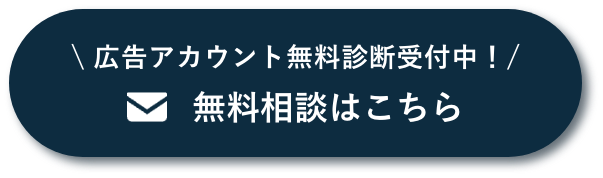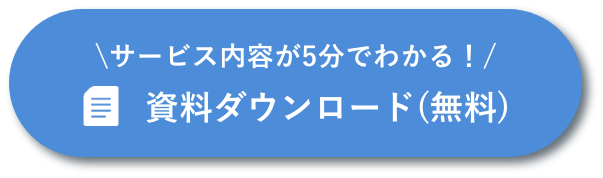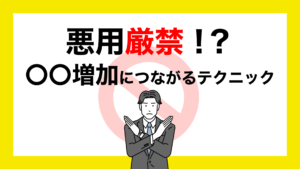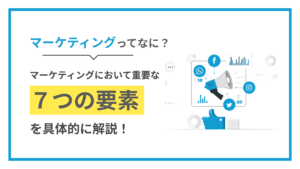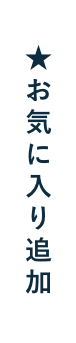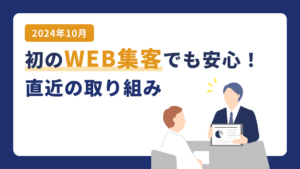

こんにちは!オールマークのさわちゃんです。
すっかり夏本番ですね…!
この記事を書いている今日は兵庫県丹波市で気温41.2度を観測し、国内の観測史上最高気温を記録したそうです。
このニュースの通り本当に年々暑くなっている気がしてなりませんが、水分補給と暑さ対策をしっかりして熱中症に気をつけていきましょう。
さて今回は、私たちの日常生活にも馴染んできた「AI」についてのお話です。
アイデアに詰まったとき、AIは頼れる相棒になる

広告運用やWEBマーケティングでは日々考えることが求められますが、
「刺さるコピーが思いつかない」「ターゲットの気持ちが読めない」「バナーや動画のネタがマンネリ化してきた」など、「自分の引き出しだけでは限界かも…」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときこそ、“生成AI”という選択肢があります。
最近では、ChatGPTやClaudeといった文章生成AIに加え、CanvaやRunway、Adobe Fireflyなどの画像・動画系AIツールも急速に進化しています。
コピー、企画、素材づくりといったクリエイティブ面を幅広くサポートしてくれる存在になりつつあるのです。
ここでは、明日から使える生成AI活用法をに5つにまとめてご紹介します。
「なんとなく便利なもの」から「使いこなせる武器」へ。
生成AIをマーケティングのパートナーとして取り入れるための具体的なヒントをお届けします。
コピーの壁打ち相手として使う

見出しや説明文がマンネリ化してきたときは、ChatGPTやClaudeなどに相談してみるのがおすすめです。
たとえば、「30代女性向けにスキンケア商材の広告文を考えて」と依頼すれば、10パターン以上の案が返ってきます。
さらに「やわらかい口調で」「共感重視で」「禁止ワードは○○」と条件を加えることで、より精度の高い出力が得られます。
ポイントは、AIから出てきた案をそのまま使うのではなく、あくまで発想のヒントとして活用することです。
精査し、自分の言葉で再編集することが大切です。
ユーザーインサイトを深掘りする
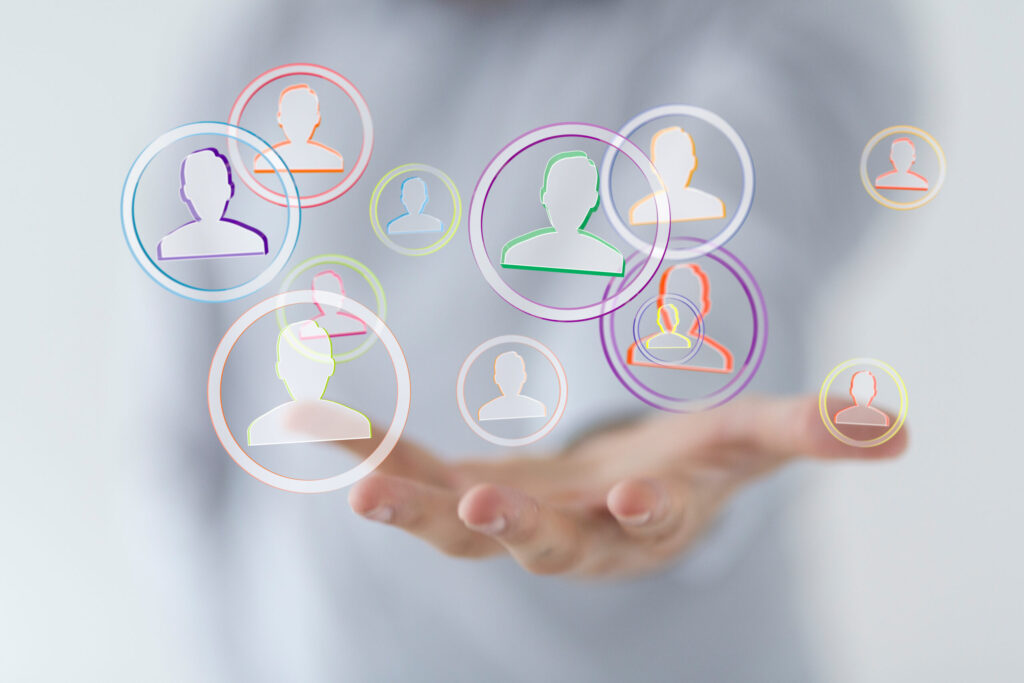
「この商材、どういう人が反応するんだろう?」
ターゲットの気持ちを深く理解したいと思っても、直接インタビューができなかったり、固定観念に囚われて本来のユーザーインサイトを見失ってしまったりすることもありますよね。
そんなときは、AIにターゲットの“気持ち”を聞いてみるのが効果的です。
例えば、
「在宅勤務で腰痛に悩む30代女性が、日常で感じる不満は?」
「40代男性が育毛について抱えがちな“言いづらい悩み”を挙げてください」
など、リアルな仮説をもとにさまざまな切り口をつくることができます。
AIは、自分では気づかなかった新しい視点や感情の切り口を提案してくれるのです。
ビジュアル制作のアイデア出しに使う
バナーや動画の構成に行き詰まったときも、生成AIは頼れる存在です。
CanvaやRunwayを使えば、構成案やフォントの組み合わせ、デザインバリエーションまでAIでサポート可能です。
さらにAdobe Fireflyのような画像生成AIを活用すれば、「ナチュラルで透明感のある世界観」などのイメージも視覚化できます。
たとえば、「自然光,ソフトフォーカス, 木のテーブルに置かれたスキンケア商品, ナチュラルな雰囲気」のようなプロンプトを入力すれば、撮影ディレクションの参考にもなる1枚が完成!
ストック写真にないビジュアルの参考画像が作れるので、LPやバナーの方向性づくりにも役立ちます。
AIで出力された画像や構成案は、実際の制作素材にそのまま使えなくても、ブレストやイメージ共有の“たたき台”として強力な武器になります。
便利な生成AI ここに注意!

AIは便利な一方で、誤用すればトラブルの原因になることもあります。以下の3点は必ず押さえておきましょう。
1.情報の正確性に注意する
AIが出す回答はあくまで“予測”にすぎず、必ずしも正しいとは限りません。
「本当に正しいか?」「この表現で問題ないか?」、人の目で必ず確認することが大切です。
2.出典や根拠の確認を行う
AIは「それっぽく見える」ことを得意とする一方で、出典のあいまいな情報や事実と異なる内容を出してくることもあります。
特に健康・医療系や統計データは、出典不明なものは使用を避けることが鉄則です。
信頼できる外部ソースでの裏取りを習慣にすることが、安全な活用につながります。
3.個人情報・機密情報は入力しない
ChatGPTなどの生成AIに対し、社外秘のデータや顧客の個人情報を入力するのはNGです。
なぜなら、入力した情報が学習や分析の対象になり、外部に保存される可能性があるからです。
必要があれば仮名化し、ChatGPTの「チャット履歴オフ」設定を使うなど、情報管理の意識が必須です。
まとめ
AIは、すべてを自動で解決してくれる魔法の道具ではありません。
けれど、うまく付き合えば日々のアイデア出しや企画立案・改善のヒントをくれる、頼れる相棒になってくれます。
大事なのは「使う・使わない」ではなく、「どう使いこなすか」です。
生成AIを正しく、そして効果的に使いこなすことで、マーケティングの成果を高める強力なサポートになります。
まずはひとつ、気になる使い方からでも試してみてはいかがでしょうか?